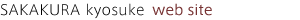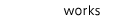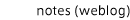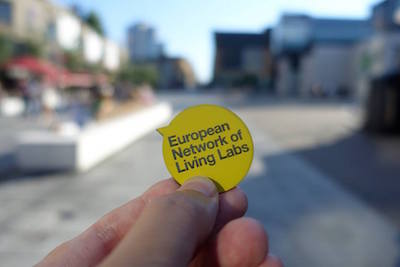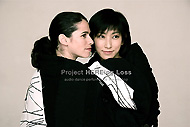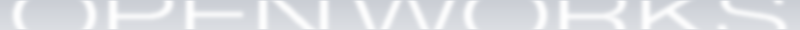
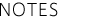
小さな神話
芝の家卒論発表会、りこちゃん・きょんみんちゃんのよるしば卒業。かなちゃんの食堂もあと1日。GI学校のインターン発表会のときも感じたのだけど、彼/彼女たちの何かを掴みとった達成感と自信に満ち溢れた姿を目の当たりにするとき、本当に感動するというか、大きなエネルギーをもらえたようで、感謝の気持ちがじわりと湧いてくる。がんばりました!って我が子のように褒めたくなるのではなく(もちろんそういう気持ちもあるけれども、むしろ)ありがとう!って心から伝えたい感じ。なんだろう、この感情は。「若者の成長を見守る」みたいな紋切り型の上から目線とは、まったく質的に違う。
彼/彼女の経験は、教えられたことを習得したり与えられたミッションを成し遂げたりという学校的な学習ではない。あるきっかけが引き金となってそれまでの日常的な常識や人間関係から離脱する(インターンや活動をはじめる)。地域社会とか多様な人たちとか学問的課題とか、とにかく彼/彼女らはそこでこれまで体験したことのなない何かに向き合い、乗り越える(とまどいながらも周囲の力を借りて実践し成し遂げる)。そして、新たな世界観をまとって戻って来る(経験を報告する)。
これ、昨晩気づいたのだけど、キャンベルの神話の構造そのままだ。若者の育ちを見守っていると思っている私たちは、実は、英雄の物語に参加し、それを間近に目撃しているのだ。未熟だった若者が非日常の世界に飛び込み、苦労しながらも私たちの遠く及ばない力と世界観を身につけ、何かを成し遂げ、ヒーロー/ヒロインとして目の前に戻って来る。その姿に私たちは畏敬の念を持たざるを得ないし、同時に、その物語を通して我々は、世界を見る新鮮な視点を与えられ、未来に希望を見出すことができる。気持ちの基層から湧き上がる不思議な感動と感謝には、人間が昔から持っていた神話的な理由があるのではないか。(こうしたコミュニティの原理的なエコシステムを、安易に「アクティブラーニング」といった枠に収めるべきではないのは言うまでもないだろう。)
みなさんの物語=小さな神話たちは、これからも私たちの地域のなかで口々に伝えられていくことでしょう。その口承の物語を語り聴くたびに私たちは、他者に対する敬意と、世界に対する新鮮な眼差しと、未来に対する勇気を瑞々しく思い出し、繰り返し生き直すことができます。本当にありがとう。そして、ご卒業おめでとうございます!

群衆と世界、ソーシャル・エンゲージド・アート。
日曜日はオフ。3331と森美術館へ。「ソーシャル・エンゲージド・アート」をめぐる議論(の内容)は目新しいものではなかったけれども、社会に関わるアートを議論することの文脈はずいぶん変わってきていると感じて(それが企画の意図でもあると思う)、もっとそれをアート以外の場ーーソーシャル・イノベーションとか都市開発とかの現場でできないものか、と思った。美術館での対話空間をなんとかそういうふうにデザインしなおすか、それ以外の対話の場で真顔でアートを扱うようにするか。いずれにしても、もっといろんなものが混交しつつ、ちゃんと向き合えるような対話の場ができたら、そこでの議論や感覚が、もう少し本当に社会が変わっていくという実感につながっていくのではないかなあ。
写真は、「N・S・ハルシャ」展より。いろんな人がそれぞれに生きているんだけど、全体的にみたら一つの織物のように。群衆と世界。
神山町へいたるくねくね道
神山町が進めている集合住宅プロジェクトについて、コミュニティづくりの観点から研究をご一緒させていただくことになり、昨日今日はその打ち合わせとか勉強会への参加とか。これからが楽しみ。
で、今日午前の田瀬さんと西村さんのトークを聞いていて腑に落ちたこと。市内から最短ルートで上がる道路は、鮎喰川じゃなくて隣の水系についた道なのだそう。道理で!車で町に入るとき「なんか神山町って突然現れるよね、不思議だよねー」と前回来たときに話していたのでした。隣の川筋からトンネルで山を抜けて町に入るので、急に神山になる違和感には理由があったのです。なるほどー。
ということで、帰りは鮎喰川に沿ってくねくね下るルートで市内に戻りました。写真はその途中の鮎喰川。この川を上っていったところに神山町がある。それを実感すると、特別なものはなにもないのになぜか感じる風景の居心地の良さの秘密に触れられたような気がするとともに、この奥にあの開けた町があることの凄さを改めて感じたのでした。とてもよい体験でした。
そしてその結果、見事に飛行機に乗り遅れ(くねくね道は夕方の市内の渋滞とも相まって予想以上に時間がかかったのでした)。今晩は空港近くに緊急泊となりました。明日は塩尻に直行します。:-)
まちづくりとは、「どんなふうに生きていきたいか?」を問い続けること
「マッチョなまちづくり」とは違う何か。これからの地域づくりにもとめられる軸が見えてきた、置賜「人と地域をつなぐ事業」の2日間でした。参加者の過半数が女性、お父さんも赤ちゃんと参加、スタッフと参加者が交互に赤ちゃんの面倒をみながら、地域と自分たちのこれからを真剣に話し合う場。障害とか子育てとかいろいろあるけれども、自分らしく生きていける地域でありたい。実際、「どんなふうに生きていきたい?」というダイアログから出てきた思いは、幸福の4因子が網羅されていたのが印象的でした。こうした幸せを人生を通じて、世代を超えて持続していける地域にするためには、大きな規模で素早くオラオラ変革していくまちづくりだけでなく、そんな想いを共有できるしなやかでゆるやかなネットワークかもしれません。ゆるやかでふわっとした活動は、ゆるやかでふわっとしている分だけ意味やニーズがぼんやりしているわけではなくて、これまでは気付かれなかった「ゆるやかでふわっとしている」ことそのものの価値を持つのではないか。こんなことを、引き続き置賜の方々と考え、実践していきたいと思います。
オープンイノベーションへの切実な期待
モントリオールに来ています。Open Living Labというカンファレンスで。日本からは私とACTANTのEmily Kimuraさんだけ。と思ったら、高齢社会研究で高名な東大のA先生もいらしていて、楽しく議論したりご飯食べたりさせていただいています。たいへん勉強になります。
私自身ははじめてLiving Labの集まりに参加した新参者ですが、日本にもどんどん取り込めそうとかむしろ日本のほうがもっと意欲的な取り組みができそう!というワクワクを感じる反面、なんというか、ヨーロッパの都市政策や社会デザインの文脈の前提になっている、「マルチステークホルダーの協働によるポスト工業社会の新しい価値創造の方法論を今きちっと確立しておかないとまずい!」という切迫感というか本気度というか真実味みたいなものが、日本に持ち帰ったとたんに、あれやこれやあるなかの一つの気の利いた(極端に言えば、「あったらいいけど、別になくても構わない」ような)ひとつの傍流に見えてしまうのが、ちょっともったいないなあ、と思ったり。うーん。なんかそういう部分をもうちょっと考え続けてみたい。
とか思いつつ、そうだ、このカンファレンスに参加した目的は、「ご近所ラボ新橋」を東京発のLiving Labとして紹介できそうかどうかを探りに来たのでした。市民が自分たちが欲しい社会を自分たちの手でつくっていくためのラボ、という点ではご近所ラボもLiving Lab。ぜひ遠くない将来、ヨーロッパで紹介したいと思います。ラボのみなさん、どうかよろしくお願いします。:-)
ポストデザインの思想
先週は、リトルトーキョーで「本当に本当にデザインするべきものとは」という集まりに参加したのでした。とてもよかった。
私は以下のようなことを即興的にお話しして、聴いてもらって、うん確かに大事なことだなと再確認できました。こうしたことを確かめられる貴重な機会でした。
いまの(少なくとも日本の)社会のしくみは、人間の生存本能に甘えすぎだと思う。こんなに子育てしにくく、老後が心配で、若者は教育を受けても職を得られるとは限らず、企業で働く1割が精神を壊す。にもかかわらず多くの人はそれでも、よく生き、よく育て、よく看取ろうとしている。社会デザインの不備を補ってあまりある、なんと強い生きるエネルギーでしょうか。でも、もうそろそろそれに甘えるのは限界ではないか。これまでとは違う思想が必要なのだと思います。これからは、人の根源的なちからに添うように、多くの人が生き生きと本能を発揮して生きられるような社会デザインが必要なのではないでしょうか。そして、そもそも「デザイン」は近代という時代の産物にして、近代的思考の典型なわけですから、すでに時代は、近代の終わりを終えていると考えるなら、近代の社会設計の思想とツールとしての「デザイン」に変わる、新しい社会づくりの知恵=「ポストデザイン」が必要なのではないだろうか。それがどんなものかはわからないけど、それを問い続けるのが「いま」なんじゃないか。そんなことを話しました。
自分で書いていてもびっくりするぐらい、大きな問いです。でも、デザインに替わる(?)何か、これからの社会づくりの基盤となる思想は、みんなで追求しなければいけないことは確か。ぼちぼちがんばります。:-)
新しい年度に向けて
右も左もわからずバタバタと過ごした2015年度も今日でおしまい。一つひとつの仕事をもっと丁寧にできたらよいのにと思いつつ、ひたすら目先のことに追われてしまった感じが残っていますが、新しく着任した学部の運営や授業準備・研究室の学生指導のほかにも、前橋や湯河原のプロジェクト、佐賀大での新しい授業、JSTや世田谷まちづくりファンドやそのほかいくつかの委員会など、振り返ってみると今年度からはじまった仕事も意外と多くて、そりゃあアワアワしても仕方ないか、と思い直す年度末。そうそう、博論は公聴会まで進みました。あと一息がんばります。:-)
明日からの新しい年度は(博論の提出が第一目標ですが)、さらにそれぞれの仕事の質を高めたいと思っています。世田谷や山形でのプロジェクトもはじまりそうだし、芝の家やGI学校の本はぜひとも今年準備を進めたい。とはいえ、経験上プロジェクト数が20を超えると、ガクッと脳みそのパフォーマンスが下がるので、新年度は「プロジェクトの上限は20まで」を守って、欲張りすぎずじっくりと向き合っていきたいと思います。
1月には、研究室のウェブサイトもオープンしました。まだまだ内容はこれからですが、研究成果もしっかり発信していきたいなあ。よかったら一度のぞいてみてください。
年のおわりに
2013年は「さすが厄年!」と感心するくらい、思い通りに進ま