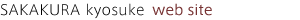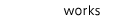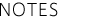
もはやミシマさんとしてのモリムラさんではない。
横浜美術館に、森村泰昌「美の教室-静聴せよ」展を観に行ってきた。
「美に至る病-女優になった私」以来の、横浜では2回目の個展。展示室は「教室」に見立てられ、モリムラ先生のレクチャーをイヤフォンで聴きながら、1時限ずつ区切られたテーマを順に巡って行く。作品はこれまでの代表作だが、先生の解説を通じて、通常の作品鑑賞がはじまる一歩手前、作家自身が絵画を眺める視線を追体験しながら作品を味わえる。鑑賞に前後の奥行きが広がる、モリムラ先生らしい展示だと感じる。
最初は、イヤフォンから流れる声のペースで移動しなければならない不自由さも感じるが、やがてそれに慣れてくると、「では次の部屋へ」と指示される受動性も心地よくなる。教室だからね、先生の言うことは聞いておこう。
6時間目までをレクチャーの進行に合わせて見終え、放課後の部屋。ここで、微かだが恐ろしい感覚を覚えた。
暗い部屋のなかで、三島由紀夫が演説をしている。鮮明な映像。正確にいうと、モリムラさんがミシマさんとして演説をしているのだが、頭のなかでまずよぎった思考は、「この解像度で、割腹はキツイよなあ」ということだった。それを考えると、少し気分が悪くなりそうですらあった。
ほんの数秒だが、ほんとうにそう思った。頭のなかに混線が生じ、作品と記憶のなかの資料映像の区別が曖昧になり、それが本物のミシマさんのような錯覚が起こったのだ。
「静聴せよ!」と、ミシマさんが叫んでいる。いやこれはミシマさんではなくて、モリムラさんだ。だいたい、記憶の片隅に残っている市ヶ谷の映像はモノクロだろう、と頭はわかっているのに、身体のほうは、どうもそれがモリムラさんに見えて来ない。フェルメールさんとしてのモリムラさんの時とは違って、ミシマさんとモリムラさんが、同じ方向から迫って来る。ほとんど同一人物だといってよい。
別に、意表をつかれたわけではない。映像の内容は大体予想もしていた。なのに、なんでこういうことになってしまったのだろうか。
ソックリだから。確かにそれもある。しかしソックリ度合いでいったら、レンブラントさんとしてのモリムラさんも引けを取らない。
おそらく一番の原因は、アレである。音声ガイドから流れる声。モリムラ先生の丁寧なレクチャーは、すべてこのための布石か。やられた、とさえ思った。(モリムラさんによるミシマさんとしてのモリムラさんの解説は、既にミシマさんとしてのモリムラさんの部屋に入ってしまっていたため、ほとんど聴こえなかった)
私は、テレビをほとんど観ない。時間がもったいないという理由ではなくて、番組の進行速度に同調させられていく感じが、心地よくはないからだ。勝手に進行する映像や音声に抗って、思考を自分のペースで行うのは難しい。何をどう考えればいいかは、ナレーターにまかせてしまったほうが何倍も楽である。自然と意識は受動化し、意図的な操作に鈍感になる。
同じように、教室、先生、最後に卒業試験、などと遠回しに脅され(?)、優しい声のレクチャーに調子づけられ、すっかり従順になっていたところ、自分のなかの三島由紀夫を、突然、モリムラさんに乗っ取られたような気分である。
この乗っ取られ人格は、もはやミシマさんとしてのモリムラさんではなく、モリムラさんが憑依したミシマさんだ。少なくとも、私の脳のなかでの構成はそうなっている。私の三島由紀夫を返せ。
このミシマさん、形式は、フェルメールさんとしてのモリムラさんや、ゴッホさんとしてのモリムラさんに似ている。でも、それらはあくまで「モリムラさん」のほうに比重が置かれており、うっかりレンブラントさんだと思い込んで、モリムラさんを後から発見したりはしない。鑑賞力が干渉して、美術家・森村泰昌の作品という前提で、これまでいろんな「としての」モリムラさんに接してきた。
そこでは、「としての」で結ばれたマネのオランピアと森村泰昌が、遠近の差はあっても、自分からある距離感を保っている。この距離感は、対象を他人事として保証してくれる。(一応、美術史専攻だから、あまり人ごととも言ってられないのだが)本質的に、ティツィアーノとマネを並べて論じるのと変わらない。
しかし、音声ガイドで受動化された自分にすべりこんできたミシマさんとしてのモリムラさんは、三島由紀夫と森村泰昌とを併置することを許してはくれず、突如として、自分の認識形式のワームホールを突いて来るかのようだった。作品と鑑賞の問題は、作品の側にあると思って油断していたところ、突然、鑑賞している自分のシステムの脇の甘さが暴かれる。自分の領域にいきなり踏み込まれる感覚。鑑賞は、誰でもなく自分自身の問題に他ならないのだ。
やられた、と思った。同時に、厭な気持ちではないが、虚しくもなる。
社会には、情報の操作が溢れている。だが、こうも手の込んだ手続きを駆使しなければ、「叫び」を「叫び」そのものとして、相手に突きつけることはできない。絵画と鑑賞者とのコミュニケーションも、同じかもしれない。ならば画家は、誰に向かって描いているのだろうか。と、そんなことを考えさせられる展覧会だった。
「静聴せよ! 静聴せよ! 静聴せよと言っているんだ!」と、(モリムラさんが憑依した)ミシマさんは叫んでいる。やがてカメラが切り替わり、遠景をフレームに入れるが、そんなミシマさんの叫びを聴いている者は、ひとりもいないのである。